 「苦沙彌」解題
「苦沙彌」解題
「苦沙彌」。「くしゃみ」と読む。時々、「くさや」と読む人もいるが、そこまで臭くない。
高校の頃、近くのJAZZ喫茶で初めてダルマ(SuntoryOld)をキープした時、そのラベルにマジックで書いて以来使い続けている。当然のごとく、ホームページを開設するにあたっても使った。
信じない人もいるだろうが、私は高校の頃は文学青年で、漱石が好きだった。漱石とは古めかしいと思われるかも知れないが、わき出してくるような漢語、ユーモアと批判精神、煩悶、歯切れのいい文体。太宰がいい、中也が好きだという同年代が多い中、私は漱石だった。
その漱石の処女作は『吾が輩は猫である』だ。
「吾が輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生まれたか頓と見當がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いて居た事だけは記憶している…」。
ニャーニャー泣いてた猫は、ある中年男性に拾われて飼われることになる。先生の職業は教師。名は、苦沙彌。
「終日書斎に入っているので、家の者は大変な勉強家だと思っている。ところが書斎をのぞいてみると、よく昼寝をしているし、時々読みかけの本の上に、よだれをたらしている。大飯を食ってタカヂャスターゼを飲む。」 インテリ面をした胃弱の小市民である。
美学者の迷亭先生や研究者の寒月君、細君や女中の御三、落雲舘中学の学生と、一癖もふた癖もある登場人物が、神経衰弱と胃病を患った苦沙彌先生をいらつかせる。
一貫したストーリーがあるわけでもなく、日常茶飯事のエピソードが続く。駄弁、駄洒落、低徊掴趣味と評されることもあるが、猫の目を通して人間社会や自分自身を批評するのが小気味よい。
漱石は、これをイギリス留学後に住んだ千駄木の家で書いた。その家は、今、明治村に移築されていて、私も訪れたことがある。「ああ、この部屋で執筆したのか…猫はここで思索にふけったのか…落雲舘からボールが飛んできたのはこの庭か」などと感慨深かった。思ったより小さい家だった。
さて、私が漱石が好きだったから「苦沙彌」を名乗っているというのでは、「半解」にすぎない。「苦沙彌」を使うには、もう一つ理由がある。
苦沙彌を使い始めた高校の時、私は僧侶の道を歩むのにかなり抵抗を感じていた。坊主は葬式ばかりしていて、生きている人の役にはほとんど立っていないと思っていた。
普通、坊さんになるには、お寺が所属する宗派系列の大学に進む。その方が、何かと優遇されるということもある。しかし、ややもすると、そこで早くも坊主社会に埋没したり、スレたりしてしまう者もいる。坊主なんたるかを考えることなく、型にはまった「坊主」になってしまう者もいる。そのコースを辿ると、一番埋没しやすいのは自分だとわかっていたからだろう、仏教系の大学には行かず、ミッションスクールに行った。若いから、やり方が乱暴だ。
「沙彌」とは、一人前ではない、駆け出し小僧のことである。サンスクリットを音写したもので、文字そのものに意味はない。
私の坊主人生は「坊主とはなんぞや」を探す遍歴だろう。探すために、手当たり次第いろいろなことに首を突っ込む。そんな、坊主なんたるかの確信を得ていない私は、駆けだし小僧以上の者ではない。宗教的な到達点も、沙彌の範疇なのだ。
青春の頃に著を発した煩悶は、中年の苛立ちとなって、いまだに私は苦の最中にある。だから、「苦沙彌」なのだ。
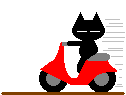 猫を真似て、残った酒を卑しく呑んで陶然となり、自坊の小池に落ちて、「南無阿弥陀仏」と唱えながら末期を迎える。「あいつらしいなぁ」と評して欲しい。
猫を真似て、残った酒を卑しく呑んで陶然となり、自坊の小池に落ちて、「南無阿弥陀仏」と唱えながら末期を迎える。「あいつらしいなぁ」と評して欲しい。
わざわざ名前の由来など説明する必要もないのだけれど、「なぜ、苦沙彌さんなのですか?」と聞かれるので…。